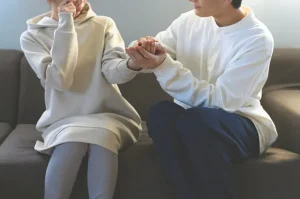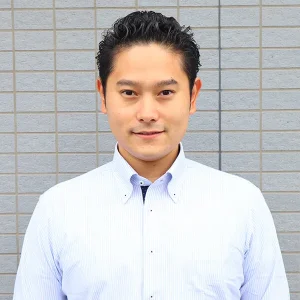2023.02.21
2024.02.23
ペットロスの乗り越え方と重症化する原因を解説

ペットロスは焦らずに、否定・交渉・怒り・受容・解決5つのステップを踏んで段階的に克服していきましょう。その具体的な方法を詳しく解説します。また、ペットロスを乗り越えるためにも重症化を防ぐ必要があるため、重症化の原因も解説します。
ペット葬儀専門の相談員に
なんでもご相談ください。
※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。

ペット葬儀専門 サポートダイヤル
![]() 0120-892-038
0120-892-038

※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。
ポイント
ペットロスとは、ペットが亡くなったりいなくなったりして、愛情・愛着の居場所をなくしたことで引き起こされる心身の症状のことを言います。家族を失って悲しむのは普通のことです。
ペットロスの克服とは、亡くなったペットのことを忘れることではありません。むしろ、ペットとの思い出を振り返り写真を飾るなどをしてペットの死に向き合うことが大切です。ペットロスになったことを恥じたり、ペットを忘れたりする必要はありません。克服に費やす時間や方法は人それぞれです。時間をかけて自分に合った方法を見つけるかカウンセリングを受けるなどして、うつ病になる前に克服しましょう。
ペットロスとは?
ペットロスとは、ペットを失うことにより悲嘆に暮れ、身体的・精神的にダメージを受けることを言います。
出てくる症状は個人差がありますが、次の項目にあるような症状が慢性的に強くなってくると、ペットロス症候群と呼ばれます。
ペットロスは大切な家族を失うことで愛情の行き場がなくなることで引き起こされるものです。
ただし、日常生活に支障が出ていたり、ペットの死後2週間たっていても改善傾向にならなかったり、どうしても苦しいときは、うつ病を発症している可能性があります。専門の医師に相談してください。
心の症状
- いないはずのペットの姿を感じてしまう
- ソワソワして物事に集中できない
- 急にパニックや不安感に陥る
- 悲観的になる
- 強い孤独感がある
- 罪悪感がある※1
- 不眠
- 所かまわずペットのことを思い出して涙が出る※1
- 好きなことでもやる気が出ない・集中できない※2
体の症状
- 疲労感・脱力感
- 摂食障害または過食
- 下痢・便秘・吐き気
- 体重の急な減少・増加
- 胃痛・胃潰瘍
- じんましんなどの皮膚炎
- 肩こりがひどい
- しびれ
- めまい※2
ペットロス症候群チェックリスト
上記の症状が出ている場合は、以下のチェックリストも確かめてみてください。
体と心の症状をまとめてみました。
- 感情のコントロールが効かない
- 急に涙が止まらなくなる
- 頭が回らない・ブレインフォグの症状がある・集中できない
- 眠れない・夜中に何度も起きる・早く目が覚める・起きるのがつらい
- 些細なことでイライラする
- 体に不調がある※3
ペットロスの克服と忘れることはイコールではない
大切な存在を失ったら、誰もが悲しみを抱きます。
それは、ペットを失ったときも同様です。ペットを失い、ペットロスにおちいることは正常な反応です。
そして、ペットロスの克服とは、ペットのことを忘れることではありません。
なぜなら、ペットとの思い出を大切にすることが治療につながるからです。むしろ、ペットのことを忘れようとするほうが、ペットロスが長引く可能性があるかもしれません。
ペットロスの克服を怖がらずに、前向きに検討してください。
ペットロスを乗り越える5つのステップ

ペットロスを乗り越えるには、5つのステップがあります。
一足飛びに焦って克服する必要はありません。ゆっくりと乗り越えていきましょう。
否定
愛するペットの死は誰しもが受け入れたくありません。
ペットロスに陥るときはまず、この「否定」の感情が付きまといます。
「なぜ」、「どうして」と考えれば考えるほど落ち込みやすく、現実から逃避しようと自己防衛機能が働きます。
この「否定」から抜け出すには相応の時間が必要です。長い人で数日を要し、ようやく否定的な感情から抜け出します。
交渉
否定から抜け出すと、次に「交渉」に入ります。
「どうかこの子を生き返らせてください」「病気は自分が引き受けるからこの子だけは」と、神様や病気、環境、ペットなどと交渉をしようと試みます。
しかし、この交渉がうまくいくことはありません。
それを仕方がなくも受け入れると、次の感情が芽生えます。それが「怒り」です。
怒り
「ペットが亡くなったのは自分のせいだ」「病気のせいだ」「獣医のせいだ」などと、受け入れ難い現実を何かのせいにし、怒りの感情をぶつけます。
中でも、「もっと早く獣医師に相談していれば」「ちゃんとケージのカギを付けていれば」など、自分に対する怒りは長引きやすく、「後悔」のかたちで後々まで尾を引く可能性もあります。
受容
怒りの感情も次第に落ち着き、ペットの死という現実を受け入れるようになります。
この「受容」までくると、ペットロスからの立ち直りも遠くありません。
ただし、不慮の事故など、自分のせいでペットが亡くなったと感じてしまう場合は喪失感を埋めきれず、より深い悲しみにおちいることが多いでしょう。
しかし、それでもこの悲しみは一生続くわけではありません。
解決
長い方で数カ月を要し、次第にペットロスが「解決」にたどり着きます。
これは、ペットのことを忘れることではありません。
ペットとの思い出を糧に、心身ともに健康を取り戻して日常にかえることこそが「解決」です。
「ペットが亡くなったのに、自分だけが普通の生活に戻っても良いものか」と考えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、そのような心配はいりません。
愛するペットもまた飼い主を愛しています。
きっとあなたが日常を取り戻すことを、ペットも望んでいるのではないでしょうか。※4
こちらの記事もご覧ください
ペットロスの具体的な克服方法
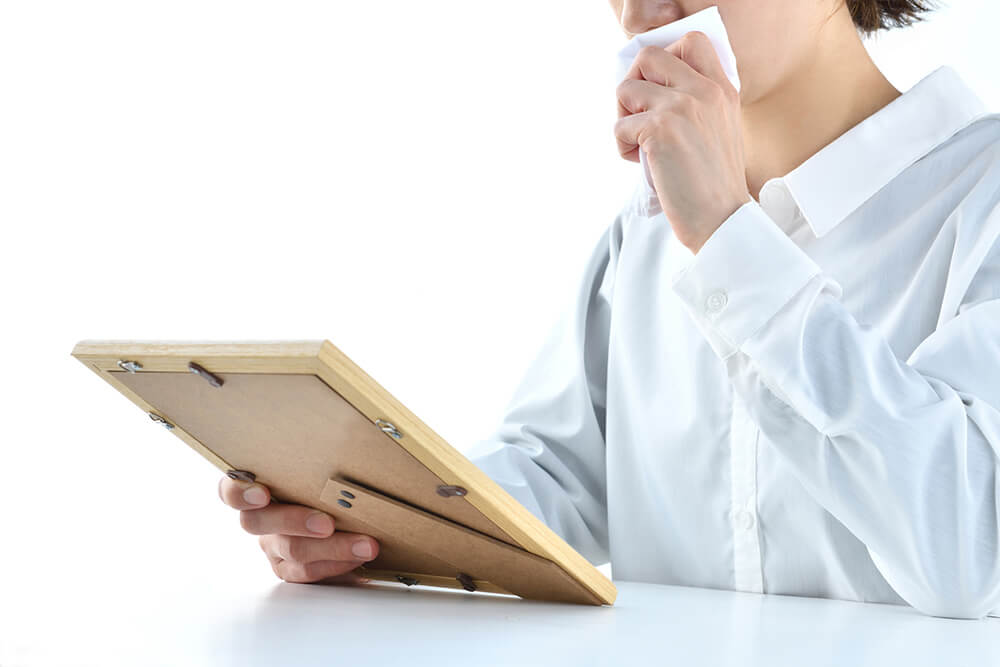
ペットロスは段階的に乗り越えていくものだとわかったら、具体的な克服方法も確認してみましょう。
もちろん、「時間」も克服に必要な要素です。克服方法をどんどん試すなどして乗り越えることを急がず、自分のペースで克服を目指してください。なぜなら、喪失感は何かをすることで完全に埋められるものではないからです。
悲しんで別れを惜しむこと
元気なふりや、無理をして別のことに取り組む必要はありません。
ペットが亡くなって悲しむことはおかしなことでも、珍しいことでもなく、普通のことです。がまんをせず、精一杯悲しんであげてください。
気が済むまで泣いて、別れを惜しむことそのものが、ペットロスの克服にもつながります。
思い出に浸る
ペットとの思い出を振り返る時間も大切です。
服やリード、食器、おもちゃなどの思い出の品は、急いで処分をすると逆効果を招くでしょう。筆者自身も、最後に愛猫を抱いた服はなかなか洗えませんでした。
気持ちが落ち着くまで手元に残し、思い出を振り返ってみてください。
そして落ち着いたら、次の項目に移りましょう。
ペットとの思い出を整理する
ペットが使った品物には思い出がたくさんつまっています。
それはペットにとっても同じことかもしれません。
気持ちが落ち着いたら、大切にしまう、あるいは飾っておいてあげてください。ペットと一緒に火葬をすることや、納骨堂に納めるのも良いでしょう。
気持ちの整理がつく前に対応してしまうと後悔が深くなり、ペットロスが長引く可能性も否めません。
ペットの葬儀事業などに取り組む業者によるアンケート調査の結果でも、ペットロスを乗り越える方法の第1位は「写真や思い出の品を飾る」でした。※5
これを見てわかるように、ペットとの思い出を忘れる必要はありません。
たくさん思い出を振り返ってあげてください。
相談や話ができる人を見つける
前出のアンケート結果の第2位に入ったのが、「家族でペットについて語り合う」でした。
家族や友達はもちろん、SNSのフォロワーも選択肢のひとつです。
ペットを愛する気持ちをよく理解してくれる人との会話は、ペットの思い出を振り返ることにもなり、結果として気持ちの整理につながります。
ペットロスがとても重たく感じるときや誰とも話せないときは、カウンセリングを頼っても構いません。
誰かに話すことそのものが、苦痛や不安を和らげることにもなるからです。
葬儀や火葬をし、しっかりと供養をすること
ペットの供養をしっかりと行うことも、ペットロスの克服に一役買います。
その理由は以下の3つにまとめられます。
- 死を受け入れられる・向き合える
- 区切りがつけられる
- ペットとの思い出を振り返る時間が作れる
このためにも、どのような供養にするのかをしっかりと考え、後悔のない葬儀や供養にしてください。※6
お墓参りをする
火葬をしてご遺骨が手元に帰ってきたら、ペット霊園や人と一緒に眠れるお墓、納骨堂のうちどれでも構いません。建墓をして「そこに行く」という行為自体が気分転換になります。
さらには、手元供養はいつまでもペットと一緒にいられて、なかなか死を受け入れられない方もいます。ペットロスを長引かせる可能性が高いと言えます。
お墓を作れば、「そこに行けば会える」という感情が芽生え、死を前向きに捉えやすくなります。そして、徐々にその街を探索してみるようになる、というプロセスです。
筆者も愛猫を失い、何年も手元供養をしていましたが突然の地震などの災害で遺骨が散乱してしまったらと考え、思い切ってペットと一緒に眠れるお墓を建墓しました。
それまでは何年もペットロスに悩んでいましたが、お墓ができてお参りに行くようになってからは、つらい心もなぜか晴れました。
納骨をするという行為も火葬や葬儀と同じく、ひとつの「区切り」なのだと感じます。
食事をとること、睡眠をとること、軽い運動を心がけること
心が疲れてしまうと、体の健康にも影響します。
まず体の健康を維持するには、睡眠と食事が不可欠です。眠れない場合は、横になるだけでも体は休まります。
できれば、日中に軽めの運動を取り入れましょう。ストレッチやラジオ体操など手軽にできるものから始めてみてください。できることから実践して、少しずつ改善していきましょう。
カウンセリングを受けること
どうしても前に進めない、2週間以上経過しても改善しない、日常生活に支障があるなど、つらいときは専門の医師を頼ってください。※7
なぜなら、誰かに相談や話をすることが、ペットロスの具体的な克服方法のひとつに挙げられているからです。
カウンセラーは相手の話を聞くプロです。どうしても心が軽くならないときは、プロに話を聞いてもらうのもひとつの方法です。
また、2週間以上症状が改善しない場合は、うつ病を発症している可能性があるからです。
この場合は、専門医の治療を受けましょう。
なぜ「2週間以上」なのかというと、うつ病の診断基準だからです。※7.8
早めに専門的な治療を行うことで、症状が改善しやすくなるうえ、社会生活への支障を最低限に抑えることができます。
こちらの記事もご覧ください
ペットロスの克服に費やす時間は人それぞれ
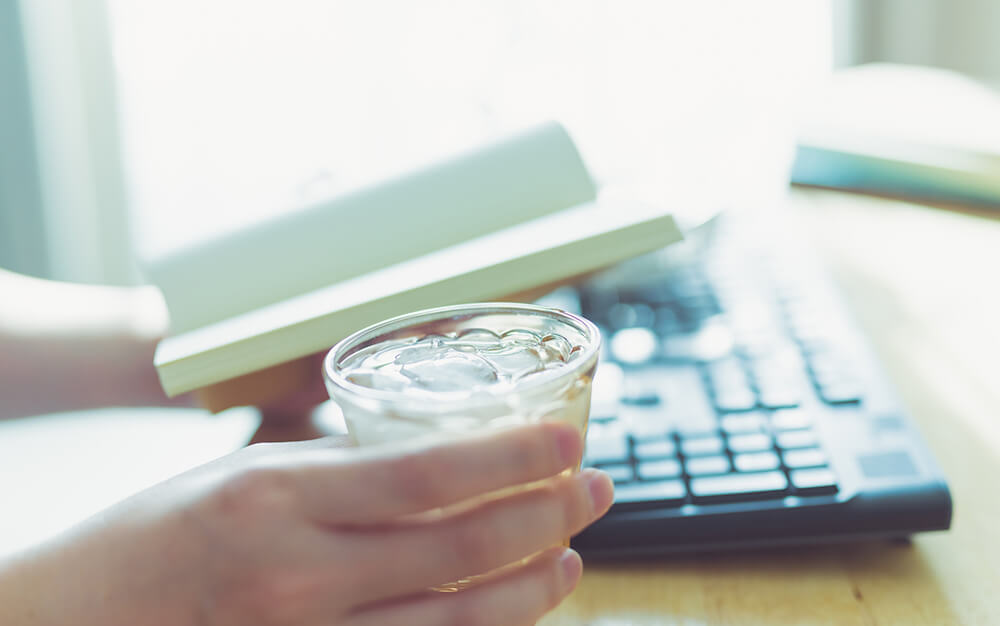
ペットロスの克服に費やす時間は人それぞれです。
ただし、大手保険会社のアンケート調査によると、ペットロスが続いた期間を「3カ月未満」と回答した方が51.0%でした。
次いで、3カ月~6カ月未満と回答した方が12.3%を占めているため、だいたいの方が半年以内に克服していると言えます。※7
ペットロスが重症化する人やペットロスの期間が長い人の特徴
ペットロスの克服方法を知るだけではなく、ペットロスが重症化する人やペットロスの期間が長い人の特徴、それぞれの原因を知ることで予防にもなり、治療につながります。
以下に記す重症化や長引かせる原因になる行為は、極力避けるようにしましょう。
罪悪感や怒りを抱え込む
ペットロスを乗り越える5つのステップの中でも、「怒り」と「受容」のハードルが高いケースもあります。
それは、ペットの死の原因が飼い主にあった場合や、「生前にもっとこうしてあげれば」と思い込んでいる場合、ペットの死の原因に対して怒りをぶつけている場合などです。
こうしたケースの場合は、ペットとの思い出そのものが死の瞬間だけに限られてしまっているともいえるため、できる限り楽しかった思い出を振り返るようにしてください。
ペットと長いときを過ごしたこと、それ自体を忘れないようにしましょう。
相談や話ができる人がいない
周囲にペットのことを話せる相手がいないときは、自分だけで解決しようとしてしまい、我慢しがちになります。
これは、重症化する一因となるでしょう。
SNSやブログでも良いので、誰かに気持ちを打ち明けてみてください。ただし、公開するということは不特定多数の人が閲覧するということです。
可能性として、心ない言葉を受けることもある点を理解しておいてください。
それを避けるために、以下の方法をおすすめします。ただし、完全に避けられるわけではないことは覚えておいてください。
- すでにSNSやブログをやっている方……仲の良い人にだけ記事を公開する
- 新しくSNSやブログをはじめる方……同じような心境の人のブログやSNSにコメントを残すことで交流を図る
また、積極的に見たいものではないため、ご遺体やご遺骨の写真は載せないことと、すぐにSNSやブログに報告する必要はなく、ペットの供養が落ち着いて心の準備ができてからでも遅くはないことの2つも、注意点として認識しておいてください。
SNSやブログでの注意点
- 公開範囲によって不特定多数の人が閲覧すること
- 心ない言葉を受けることもあること
- ご遺体やご遺骨の写真を載せないこと
- 急いで報告する必要はなく、ペットの供養が落ち着いて心の準備ができてからで構わないこと
ペット中心の生活をしていた
ペット依存と言われるほど、ペットが生活の中心になっていた場合も、ペットロスが重症化する一因です。
何をするにも常にペットを優先してしまい通常の社会生活が送れなくなると、友人や家族関係も破綻しやすく、ペットを失った際に話せる人がいないことにもつながります。※9
ペットロスが重症化した飼い主の特性をアンケートで調査したところ、「周囲の人とあまり会話がない」が80%にのぼりました。
「ペットが死んだ悲しみを友人や家族に伝えられず、悲しみを吐き出す場所がなかった」が70%、「「自分が好きな物はペットも好きなはずだ」と思い込んだり、常にペットと同じように生活をしたりして、ペットと自分の気持ちや生活の境界があいまいであり、極度のペット依存状態にあった」が40%という結果です。※10
「ペット依存になりやすい飼い主の特徴」を獣医師にアンケート調査をした結果は以下のとおりです。
- ペットを人間の子どもと同じように考えている
- ペットが病気やけがをすると激しく動揺する
- ペットの世話をすることを生きがいにしている
- ペット以外に話す相手が少ない
- 1頭(匹)だけを飼っている
- ペットに多くのお金をかけている(一般的なお金のかけ方よりも大きい)
- ペットに関する情報(病気など)を必要以上に調べている
- 一人暮らしをしている
他に、死別や仕事のリタイヤなど、何らかの喪失体験をした方も、ペット依存になりやすい飼い主の特徴として挙げられます。※10
ペットを自分の一部のように大事にすることは素敵なことですが、依存してしまうのは良くありません。
「飼い主がペット依存に陥らないために獣医師がすべき対応」として、「ペットに関して話できる仲間を紹介する」が挙げられたアンケート調査もあります。※10
飼い主である前にひとりの人間として、周りとの関わりも大切にしましょう。
周囲との感覚の不一致
ペットの話ができれば誰でも良いわけではありません。
ペットに対する考え方や、悲しみの度合いの違いにより精神的な支えをなくすこともあり得ます。
できるだけ同じ境遇を経験した人や、ペットに対する感覚が似通った人に話をすると良いでしょう。
また、ペットロスによって仕事や学校を休む際や、家事や趣味に力を割けられなくなったときに、理解を得られないこともあります。
しかし、それを怖がって自分の心にふたをすることや、他人に一切話さないことはペットロスの悪化につながります。
どうしても話せる相手や理解者がいないときは、カウンセリングを頼りましょう。※7
感情表現が苦手
自分の感情を表に出すことが苦手な方は、悲しみや怒りを自分ひとりで抱え込みやすく、発散させることができません。
周囲には平気なふりをして、自分ひとりで抱え込もうとします。
気持ちの準備の問題
急死や事故死など、ペットの死に対する準備ができていないときや、飼い主自身に辛いことがあったタイミングでペットを失ったときは、ペットロスが重症化しやすいと言えます。
これに関しては防ぎようがないため、ペットロスが辛いと感じたらカウンセリングを頼ってください。※5
他に悩みがある人
ペットに関係なく、何らかの悩みがあった方は、ペットが癒やしになっていた可能性が高く、ペットロスが長引くでしょう。
この場合は、早めに悩みを解決しておくしかありません。
悩みはそのままにせず、どんなものでも早期改善に向けて努力をしましょう。※12
ペット以外の趣味がない人
ペットロスが長引く人の中には、ペット以外に趣味がない方がいます。これは、ペット依存と似ています。生活の中でストレス解消や趣味の時間にペットとばかりいると、ペットが亡くなったときに、他にストレス解消や楽しみの選択肢がなくなり、ペットロスが重症化してしまうでしょう。
逆にペットロスが軽く済む方は、ペットが亡くなったことで他の趣味に避ける時間が増えたと前向きにとらえられる方や、ペットが新しい趣味を教えてくれたと思える方です。
初めてペットを亡くした人
大切な家族の死は、何度経験してもつらいものです。しかし、全く経験がない方と、過去に経験がある方には大きな違いがあります。
過去の経験があれば心の準備はもちろん、火葬や葬儀の準備、お別れの仕方など、ある程度気持ちの準備ができています。※12
ペットを長く飼っていた人
長生きをしたペットを亡くすと、その反動は大きくなります。依存していたわけではなくても、長く生きたペットの場合は、一緒にいた時間も多く、注いできた愛情の量も多いからです。
ペットロスの主なきっかけが、愛情が行き場をなくすことであることを考えれば、その愛情が多ければ多いほど症状は重く、長引くでしょう。※2
こちらの記事もご覧ください
ペットロスが長引くとうつ病になることも…
ペットロスからペットロス症候群になった後、うつ病を発症することもあります。
ペットロスによる気持ちの落ち込みは、ペットのことを思い出して涙が出る、ペットのことを思い起こす場所やシーンで涙が出るなど、ペットに関連することで起こる悲しみが多くを占めます。
喜びに関しては、ペットとの楽しい思い出を思い出せば、少し心が和らぎます。
反面、うつ病になるとどんなことに対しても落ち込みが続き、涙が出たり、嬉しいことがあっても心が反応しなかったりします。さらに自己否定が続き、自分には何もできない、自分には価値がないと、自分を追い込んでいきます。
ペットが亡くなってから長くペットロス症候群の症状で日常生活に支障が出ている場合はうつ病を疑い、専門の医師を頼ってください。※1.7
ペットのペットロスについて
多頭飼育の場合、ペットもペットロスになることがあります。
有名なのは文鳥の後追いです。
文鳥は仲間や配偶者(つがい)に多くの愛情を注ぐため、相手が亡くなってしまうと数週間後には、残っていた文鳥も亡くなることがあります。
さらには、他の動物でもペットロスのような状態になることがあると言われます。
2022年の2月に、多頭飼育をしている家庭で犬が1頭死んだ場合、生き残った犬にどのような兆候があったかのアンケートを実施し、その結果を論文にまとめたものがNatureに掲載されました。※13
一方の犬が亡くなり、生き残った犬の行動の変化は以下のとおりです。
67%:飼い主の注意をひくようになった
57%:遊びが減った
46%:活動レベルが低下した
35%:睡眠が増えた、怖がるようになった
32%:食べる量が減った
30%:吠える量が増えた※13
前述のNatureに掲載された論文には、「友好的な関係を築いていた場合や、親子関係だった場合はより強力な行動変化と関連していた」と記載があります。
新しいペットのお迎えについて

新しいペットをお迎えすることは、ペットロスの軽減や克服につながることもあります。
新しい生きがいが生まれ、お世話をすることが行動力や意欲につながります。さらに、亡くなった子にしてあげられなかったことを後悔だけで終わらせず、活かすことができるからです。
ただし、新しいペットを迎えるには気を付けなければならないこともあります。
それは、タイミングです。
まずは必ず家族と話し合い、家族全員心の準備ができていることを確認する必要があります。
次に、ペットカフェや友達のペットなどを実際に触ってみてください。罪悪感が生まれないかどうか、お迎えしたい気持ちが強まるかどうかを確認してみましょう。
そして一番大切なことは、どのペットにも別れがあることを理解することです。
別れを一度経験している方ならば、心の準備ができているとも考えられます。ペットとの別れの際に、感謝の気持ちを伝えられるような準備は整っているでしょうか。
衝動的に新しいペットをお迎えしてしまうと、こうした気持ちの整理がついていないことが多く、亡くなったペットと新しいペットを比べてしまうこともあります。そうなると、お互いがストレスになり、体調を崩すこともあるでしょう。
多頭飼育の場合は相性の問題もあります。ペットロスの軽減を期待して、衝動的に新しいペットを飼うことは避けましょう。
こちらの記事もご覧ください
まとめ
- ペットロスの克服とは、ペットのことを忘れることではない
- ペットロスを乗り越えるには、否定・交渉・怒り・受容・解決の5つのステップを経る
- ペットロスの具体的な克服方法は、悲しんで別れを惜しむこと・思い出に浸ること・ペットとの思い出を整理すること・相談や話ができる人を見つけて話すこと・しっかりと供養をすること、食事をとること、眠れなくても横になることなど
- ペットロスが重症化する原因や長期化しやすい方は、罪悪感や怒りを抱え込む・相談や話ができる人がいない・周囲との感覚の不一致・気持ちの準備不足・ペットとの別れが怖い方・他に悩みがある方など
- ペットロスの克服に費やす時間は、多くの人が3カ月未満
- ペットロスが長引くとうつ病になることもあるので、ペットが亡くなって2週間以上ペットロス症候群の症状が続き、日常生活に支障が出ている場合は専門の医師を頼ること
- 新しくペットを飼うことは慎重に検討する必要がある
よくあるご質問
-
Q
ペットロスはどうやって乗り越えたら良いですか?
Aペットロスを乗り越えるには、写真や思い出の品を飾るなどしてペットとの思い出を振り返り、ペットを思いながら悲しむことが一番大切です。他に、きちんとした供養をすることや話ができる人を見つけるなどが挙げられます。
-
Q
ペットロスはどのくらい続きますか?
A大手保険会社のアンケート調査によると、3カ月未満という回答が51.0%でした。ただし、これには個人差があり、1年以上続いている人もいます。
-
Q
ペットロスで病院に行くとしたら何科ですか?
Aペットロスは精神に関係する病気なので、精神科で治療を行います。カウンセリングや投薬などを行い、回復に向かいます。
-
Q
ペットロスはぶり返すことがありますか?
Aあります。ペットロス初期の頃は、何度も繰り返し悲しみをぶり返したと思いますが、治ったと思っても数カ月後に突然悲しみがぶり返すこともあります。※14
-
Q
やってはいけないペットロスの克服方法は何ですか?
A亡くなったペットのことを無理に忘れようとすることは、ペットロスの長期化を生む可能性があります。また、衝動的に新たなペットを迎えることもやってはいけない行為です。
※1:ペットロス症候群とは?うつ病との関係と予防と対処法(閲覧日:2024/2/20)
https://www.shinagawa-mental.com/column/psychosomatic/pet/(2023/3/29)
※2:ペットロスの症状に当てはまっていませんか?心身ともに休養しよう(閲覧日:2024/2/20)
https://www.petsogi-nabi.com/pet-loss-symptoms/(2023/11/27)
※3:【臨床心理士解説】ペットロス症候群かも?セルフチェックで見るべき6つの言動(閲覧日:2024/2/20)
https://reme-nomal.com/article/224501/(2022/9/27)
※4:ペットロスを乗り越えよう
https://www.petsougi.net/feature/feature02.html
※5:<ペットの飼育経験のある391名に聞く「ペットロス」に関する意識調査> ペット飼育者の約7割が「ペットは家族と全く同等」「ほぼ同等」と回答 ペットロスを乗り越える方法第1位は「写真や思い出の品を飾る」(サンセルモsorae調べ)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000092150.html
※6:ペットロスとは?症状や周りの接し方、悲しみから克服する方法を解説
https://life.saisoncard.co.jp/family/pet/post/c58/
※7:ペットロス症候群(グリーフケア含む)(閲覧日:2024/2/20)
https://hidamarikokoro.jp/blog/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%B9%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%EF%BC%88%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%B1%E3%82%A2%E5%90%AB%E3%82%80%EF%BC%89/(2022/12/26)
※8:ペットロス症候群とは?うつ病との関係と予防と対処法(閲覧日:2024/2/20)
https://hidamarikokoro.jp/speciality/melancholy/
※9:愛犬の愛し方、偏っていませんか? 「愛犬依存」とは(閲覧日:2024/2/20)
https://dog.benesse.ne.jp/withdog/content/?id=156724(2023/5/24)
※10:ペットロス症候群に陥りやすい飼い主の特性と獣医師がすべき対応(閲覧日:2024/2/20)
http://jissen-kenkyu.la.coocan.jp/img/file133.pdf(2023/5/24)
※11:ペットロスできついと感じたら?重症化する人の特徴と考え方を解説
https://omoshirocase.com/blog/28154/
※12:ペットロスできついと感じたら?重症化する人の特徴と考え方を解説(閲覧日:2024/2/20)
https://www.amimono.co.jp/wp-memory/soudan/post-7854.html(2023/11/28)
※13:Domestic dogs (Canis familiaris) grieve over the loss of a conspecific(閲覧日:2024/2/20)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-05669-y(2022/2/24)
こちらの記事もご覧ください
※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数
この記事の執筆者

竹田 恵氏
ペットシッター士
ライター
竹田 恵氏
ペットシッター士
ライター
2017年よりライターとして活動中。子供の頃から動物好きで、猫、ハムスター、うさぎの飼育経験あり。現在はシーズー犬と一緒に暮らしている。犬は他の動物と比べて人間と密な生活になるため、ペット関係の資格を取得した。
運営元情報
| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |
| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |
| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |
コラムの執筆と編集について
ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。
以下のページよりご確認いただけます。
【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/






 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ