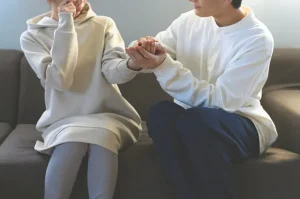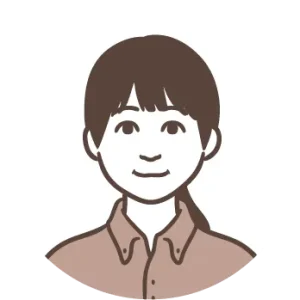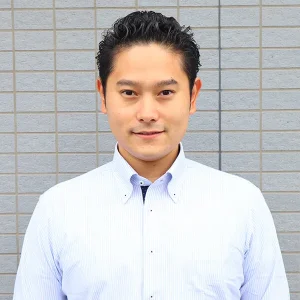2022.02.25
2025.09.23
ペットロスについて~愛猫との別れの悲しみを癒すのに必要なこととは?

ペットロスは誰にでも起こりうる正常な反応です。なぜなら、大切な人が亡くなったら、誰だって悲しいからです。この悲しみのことをペットロスと言います。この記事では、ペットロスについての概要や癒し方、間違った対応などを解説します。
次のページで実際にお見積りをご確認いただけます
※弊社スタッフからご連絡させていただく場合がございます。
愛猫との別れがきっかけとなるペットロスとは

「ロス」とは失うという意味です。
何かを失って悲しくなるのは正常な反応です。
家族、友人、恋人などが亡くなったら誰しも悲しむことでしょう。
家族であるペットが亡くなって悲しむことは普通のことです。特別なことではありません。
これを「ペットロス」と言います。
ペットロスが深刻な状況になり、からだの不調を招くまでになると、「ペットロス症候群」に呼称が変わります。
しかし、ペットロスはペットが亡くなったときだけに起こることではないのです。
詳しく解説していきましょう。
ペットロスはペットが生きていても発症する
ペットが生きているのにペットロスになることもあります。
これは、ペットとの生き別れによるものです。
特に高齢者は、入院や老人ホームへの入居などでペットを他の人に引き取ってもらうことがあります。このようなときにも、ペットロスを発症することがあります。
筆者もこの経験があります。
ペットが大きな病気をして生死の境をさまよい、入院していたときです。
ペットの入院中は自分自身生きた心地がせず、仕事も生活も手に付かない状態が続きました。
数年経った今でもふと思い出すときがあり、感情が不安定になることもあります。
ペットの生死に関わらず、どうしても忘れられない別れを経験すると、なかなかペットロスを克服できません。※1
ペットロス症候群の症状

ここからはペットロス症候群について具体的に確認しましょう。
からだの症状
まずは、からだに出てくる症状を確認します。
- 不眠
- 食欲不振
- 摂食障害(拒食・過食)
- 胃の痛み
- 息苦しさ
- 疲労感
- からだの痛み
- めまい
- じんましん
筆者がペットロスのときは、不眠と食欲不振、息苦しさ、めまい、疲労感を経験しましたが、それはとても辛いものでした。
ペットロス症候群になると、周囲の人の支えと理解なしには生活できないこともあります。
心の症状
ペットロス症候群は、心の不調の方が深刻になり呼応するように肉体的不調も表れます。
自分ひとりの力では克服できないと感じるときや、症状が1か月以上続くようでしたら無理をせず、専門医を頼りましょう。
- ひどく落ち込む
- 自分や他人を責める
- 喪失感や罪悪感・虚脱感
- 孤独を感じる
- どんなものにも関心や興味・意欲を持てなくなる
- 感情が不安定になる
これらの症状がひどくなってくると、うつ状態になっていきます。
うつ状態になり、日常生活に支障が出てきたら我慢をせず、必ず専門医を受診してください。ペットロス症候群からうつ病になるケースは、珍しいことではありません。※2
愛猫のペットロスを癒すには
ここからは、ペットロスの乗り越え方について解説します。
ただし、これらの方法を行えば、必ずペットロスを乗り越えられるとは限りません。
ご自分に合わないこともあります、これらはあくまでもひとつの方法です。
愛猫をしっかりお見送りする
ペットロスから乗り越える第一歩は、愛猫の死を受け入れることにあります。
そのため、亡くなってしまった愛猫をしっかりと供養することは、ペットロスを癒す近道といわれています。
葬儀や納骨による目に見える形での区切りは、心を安定させてくれます。
思い切り泣いてよい場を作ることと、きちんとした弔いをしたという安心感から、気持ちに区切りがつきました。
さらに、葬儀や納骨をすれば愛猫が亡くなった事実を受け止めることが出来ます。
さらに、納骨してお墓参りをすることが気分転換になることもあり、霊園への納骨はとても大切なことと考えましょう。
葬儀をして終わりではなく、供養・納骨を行うことで、愛猫が亡くなった現実を受け止め、気持ちを整理できます。
愛猫の形見を作る
愛猫の写真を入れたキーホルダーやペンダント、コップやバッグなどは、写真屋さんなどで手軽に作れます。
ご遺骨を入れられるキーホルダーや、愛猫の毛で作られる猫毛フェルトも人気です。
これらの形見と常に一緒にいることで「いつも一緒にいてくれる」安心感を得られるでしょう。※3
愛猫を亡くした悲しみや経験を誰かに話す
誰かに辛いことを話すことはとても良いことです。
話しているうちに心が整理され、助言を受けなくても心が安定することもあります。
話し相手は必ずしも精神科医やカウンセラーである必要はありません。
気兼ねなく話せる家族、友達、SNSのフォロワー、誰でも構いません。
今の辛い気持ちを共有し、話を聞いてくれる人に話してみましょう。
ただし、話すことが辛いときは無理に話をせず、ひとりの時間を作ってください。
ゆっくりと心とからだを休めることも、ペットロスを癒すのに必要なことです。
獣医師へ相談する
精神科医に相談しにくいときは、獣医師に相談してみても良いでしょう。
獣医師は沢山の飼い主を見ています。中にはカウンセラーを置いている動物病院もありますので、相談を考えてみてください。
特に、病気で愛猫を亡くしたことを後悔しているときは、病気について詳しく聞いてみるのもおすすめです。
ただし、愛猫の死を怒りに変えて、相手にぶつける行為は慎みましょう。※4
症状が長引く場合は専門家へ相談を
一月以上ペットロスが長引くときや、ペットロス症候群を発症したとき、うつ状態になってしまったときは、ためらわずに精神科医やカウンセラーを頼りましょう。
ペットロスを長引かせる良くない対応

ペットロスを長引かせる原因はあります。
特に周囲の人の間違った対応はペットロスが長引く要因になりがちです。しかし、それはペットロスになった当人を傷つけようとして言っている言葉ばかりではないということを、頭の隅に置いておきましょう。
周囲の環境
ペットロスになると、周りの人との価値観の不一致に悩むことがあります。
特に、「新しいペットを飼えば良い」「多頭飼いで良かったね」など、亡くなった愛猫以外のペットを可愛がることを勧める行為に、心を痛めることは多いでしょう。
もちろん、新しいペットを飼うことがいけないわけではありません。
愛猫を亡くし、寂しい気持ちからそれを望むなら、新しい出会いを求めることは間違いではありません。
しかし、この言葉で傷ついたなら、相手の言葉をうのみにせず、新しいペットを検討する段階ではありません。
亡くなってすぐに新しいペットを飼うと、「あの子は死んだのにこの子はなんで元気なのか」と、憎しみの感情を抱いてしまうこともあるからです。これはお互いを不幸にしてしまいます。
さらに、「ペットなんかの死で仕事を休むな」「そんなに悲しいの?」などと言われることもあるでしょう。
もしも、職場がペットの死で休むことをよしとしないような雰囲気なら、それを隠して休むのもひとつの選択肢だと考えてみてください。
ペットロス症候群になっているなら、なおさら無理をせず、休むことが大切です。
また、ペットを飼ったことがない方には、ペットの死を思い切り悲しむことを理解できないこともあります。そのことは、事実として理解しておくことも大切です。※5
後悔の残る突然の別れ
ペットロスを強める原因のひとつが、強い罪悪感や後悔、突然の別れです。
交通事故や急病などもこれに該当しますが、その原因が飼い主にあるときは、さらにひどく落ち込み、自分を責めてしまいます。
定期的な健康診断を欠かさないようにし、具合が悪そうなときはできるだけ早く獣医師の診察を受けさせてください。
ペットの健康管理は、飼い主の義務です。少しの異変にも気付けるように、日ごろからコミュニケーションをとっておきましょう。
そして、窓やドアの開閉に注意をし、猫の脱走による不慮の事故を防ぐことが大切です。
また、猫にとっての適切な飼育環境を整えることも忘れないでください。
食べ物を床に落とさない、猫が届く範囲に食べ物を置かない、ビニールやコンセントなどの危険物に対する注意や工夫もしておきましょう。※6
悲しみを怒りに変えるのは良くない
ペットの死を誰かのせいにする、気持ちを理解してもらえないストレスで当たり散らすのも、ペットロスを長引かせる良くない行為です。
ペットを失ったことで自分を責める行為は、きっと誰もが行ってしまうことでしょう。
しかし、行き過ぎた行為は自分の心を傷つける行為に他なりません。
大切なのはかけがえのない幸せをくれた愛猫に感謝をし、見送ってあげることです。※5
まとめ
- ペットロスは普通のこと
- ペットロスはペットが生きていても発症する
- 主なペットロスの症状とは、不眠・食欲不振・ひどく落ち込む・自分を責める・感情が不安定になること
- ペットロスが深刻になり、からだの不調を招くことを「ペットロス症候群」と呼ぶ
- 何をしても楽しくない・生きていることが虚しい・生きるのが辛い・全く眠れないなどがあればうつ病になっている可能性があるため、専門医を受診しよう
- 葬儀・納骨・形見・人に話す・休むことはペットロスを癒す一助になる

 もしもにそなえる生前見積もり
もしもにそなえる生前見積もり
ペットちゃんのもしもの時、慌てて悔いの残るお別れとならないよう、事前準備が必要です。ペトリィでは生前のご相談も可能です。

自宅での葬儀

家族立ち合い

セレモニー

家族でお骨上げ

骨壺に納めご返骨

霊園への埋葬
※1:ペットロスと向き合うため
https://www.pet-no-shikaku.com/feature/petloss3
※2:【ペットロスとうつ】自己解決が困難な場合は早めに医療機関へ
https://www.shinjuku-stress.com/column/psychosomatic/pet/
※3:愛猫を失った悲しみ 辛いペットロスを癒やすには
https://sippo.asahi.com/article/11889711
※4:獣医師からペットロスのカウンセラーに転身。愛猫が誘った新境地
https://news.1242.com/article/133968
※5:ペットロスとは?症状や克服方法、周囲の人の接し方について
https://pedge.jp/reports/petloss/
※6:ペットロス症候群とは?症状やチェック方法、乗り越え方を徹底解説!
https://moffme.com/article/1168
※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数
この記事の執筆者

竹田 恵氏
ペットシッター士
ライター
竹田 恵氏
ペットシッター士
ライター
2017年よりライターとして活動中。子供の頃から動物好きで、猫、ハムスター、うさぎの飼育経験あり。現在はシーズー犬と一緒に暮らしている。犬は他の動物と比べて人間と密な生活になるため、ペット関係の資格を取得した。
運営元情報
| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |
| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |
| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |
コラムの執筆と編集について
ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。
以下のページよりご確認いただけます。
【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/






 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ