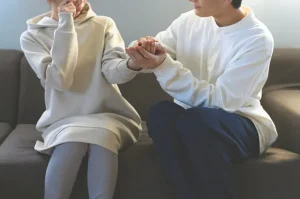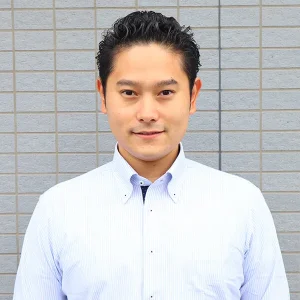2021.06.18
2023.12.13
猫が死ぬ前にみせる兆候、あなたがそのとき愛猫にできること。

猫は死ぬ前、どのような行動をとるのでしょうか?死期を悟って飼い主の前から姿を消すと言われているのは本当でしょうか?死ぬ前の兆候や行動、バイタルサインの変化を獣医師が解説します。また、最期のときが近づいてきた愛猫にしてあげられることについても紹介しています。
ペット葬儀専門の相談員に
なんでもご相談ください。
※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。

ペット葬儀専門 サポートダイヤル
![]() 0120-892-038
0120-892-038

※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。
この記事の監修者

増田 国充氏
ますだ動物クリニック院長 / 獣医師
増田 国充氏
ますだ動物クリニック院長 / 獣医師
獣医師、防災士、2001年北里大学卒
2007年ますだ動物クリニック開院。診療に東洋医療科を加え、鍼灸や漢方による専門外来を実施。運動器疾患に対して鍼灸による治療を積極的に取り入れ、県内外から症例に対応する。また、鍼灸・漢方等で国内外で講演を実施。動物看護系専門学校非常勤講師兼任。
ポイント
猫が死ぬ前にみせる兆候は、ぐったりする、攻撃的になる、食欲が低下するなどの行動の変化に加え、脈拍数や呼吸数、体温などのバイタルサインの変化が挙げられます。飼い主にできることは、これらの兆候にできるだけ早く気づき、適切な治療を受けさせることと、QOL(生活の質)を維持してあげることです。
猫と最期のとき

猫の寿命は15年前後とされていますが(※1)、死の直前に飼い主の前から姿を消すと言われています。仮に寿命を迎える前に飼い主の前から姿を消すならば、猫は自分の死を自覚しているということになります。
人に最も近い動物である霊長類のゴリラでは、死の概念を理解している可能性があります(※2)。しかし、猫においては死の概念を理解しているかはわかっていません。現在、猫が死の直前姿を消す行動は、体力が衰えた猫が何かしらの身体の危険を察知して安全な場所に姿を隠すことが原因ではないかと言われています。
猫をとりまく社会情勢や飼育環境の変化により、衰弱した猫が室外で死亡する可能性が高い「外飼い」ではなく、「完全室内飼い」が推奨されるようになりました。死の直前になり身体の異常を感じ取り不安になった猫が、軒下などの野外にある隠れ家ではなく、愛する飼い主の側やキャットゲージなどの安全な場所で寿命を全うするようになり、死の直前に姿を消す猫が減ったという一説もあります。

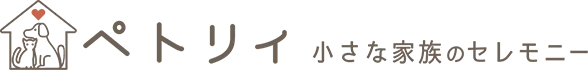 もしもにそなえる生前見積もり
もしもにそなえる生前見積もり
ペットちゃんのもしもの時、慌てて悔いの残るお別れとならないよう、事前準備が必要です。ペトリィでは生前のご相談も可能です。

自宅での葬儀

家族立ち合い

セレモニー

家族でお骨上げ

骨壺に納めご返骨

霊園への埋葬
猫の死ぬ前の兆候
室内で飼育されている猫が、死の直前に姿を消すことがないとすれば、実際にどのような変化がみられるのでしょうか?
老衰した猫が死の概念そのものを理解しているかは定かではありませんが、体調の悪化は猫の行動をなんらかの形で変化させます。
行動の変化
死ぬ前の猫では普段と異なる行動がみられます。体調の悪化により身体が辛く、動くことが困難な猫では、ぐったりとする、活動性が低下するなどの症状がみられ、死因が痛みを伴う場合、性格が攻撃的になる、触られることを極端に嫌がるなどの症状としてみられる場合があります。
また、食欲の低下がみられることもあります。猫が好物や嗜好性の高い食べ物を口にしないときには、体調の悪化がある程度まで進んでいると考えられます。
死の直前、猫がよく鳴くと一般的に言われていますが、猫は不安を感じると鳴くことがあり(※3)、猫は体調の悪化を不安として感じている可能性があります。
バイタルサインの変化
バイタルサインとは動物の状態を表す身体的な指標です。心拍、呼吸数、体温などが含まれ、正常値の目安が知られています。バイタルサインは猫によって個体差があり、猫の興奮や不慣れな手技によっても正しいバイタルサインが観察できません。日頃からバイタルサインの測定をおこなうことで、飼い主と猫が手技に慣れている状態にすると同時に個体ごとの正常値を知っておくとよいでしょう。
猫の正常な心拍数は1分間に120~150くらいです。死ぬ前の猫では身体の異常により心拍数は増減します。強い痛みを感じている猫では、アドレナリンの分泌により心拍数が増加します。逆に、身体全体の働きが衰えている場合では心拍数は低下すると考えられます。
個体差hありますが正常な呼吸数は1分間に20~30回前後であり、心拍数と同様に死ぬ前の身体に起きる異常を反映します。呼吸数の顕著な増加や、開口呼吸は痛みや息苦しさを表しています。
猫の正常な体温は38~39℃であり、人の平熱よりもかなり高温ですが、死ぬ前の猫の体温は低下していきます。感染症などの炎症が引き起こされる疾患では体温は上昇しますが、死の原因となるショック症状が進行すると体温は低下します。

我々人間と猫とでは、ことばを通じたコミュニケーションをとるのは確かに難しい部分があります。
とはいえ、猫は行動や表情を通じて絶えず何か情報を示しています。その一つがバイタルサインです。TPRともよばれる体温、心拍数、呼吸数のほか、トイレの回数や排泄したものの様子、活動性、性格の変化など、実はあらゆる場面で猫の気持ちや体調の様子を図ることができるヒントはたくさんあるのです。
重要なのは、普段の「正常」を知ることです。普段の様子がどんなものであるかを観察しておけば、不調が生じたときに早い段階で気づくことにつながります。ひいては、猫の健康寿命を延ばす一つの手段ともなりうるのです。
プロフィール詳細を見る
こちらの記事もご覧ください
猫にしてあげられること

いままで人生を共にしてきた愛猫が最期の時を迎えるとき、飼い主には何ができるのでしょうか?命あるものとして動物の死は避けることができない出来事ですが、より穏やかな死のためにできることはあります。
飼い主の気づき
猫の死には老衰や疾患などの原因があります。そのなかには事故や急性の経過を辿る疾患など、飼い主が気付いたときには手を尽くすことが難しいこともありますが、猫の死因として多い腎臓病などの慢性疾患や、老衰や寿命に関係した死ではゆっくりと身体が衰えていく場合もあります。
猫が緩やかに衰えていくとき、飼い主がそのことに気が付くのはとても重要です。疾患の治療や、老衰のケアは猫の余命をより長く、快適なものにするからです。
猫の衰えに気が付くためには毎日きちんと観察することが重要です。食欲や元気、体重の変化は体調を表している場合があります。排便や排尿の頻度や内容物の様子も忘れずに観察するようにしましょう。
猫の体調不良に一番早く気が付いてあげることができるのは飼い主です。体調不良を感じたときは動物病院を受診してください。
QOLを維持する
体の衰えた猫は、健康だったときにできたことが難しくなっていきます。筋力や関節の衰えは、いままで俊敏に乗り越えていた段差を大きな障害物に変化させ、顎の力の低下により、固形物を食べるのが難しくなることもあります。また、排尿や排便、毛づくろいを上手におこなえなくなることで大きなストレスを感じる猫もいるでしょう。
QOL(Quality of life)とは「生活の質」を表す言葉です。上記のように思うような生活をおこなえなくなった猫ではQOLは低下していると考えられます。猫の行動がもたつく、動きが遅くなったと感じた場合、猫の行動が段差を利用しなくても完結するような環境をつくることでQOLを維持することができます。
食欲が低下している猫では、固形食が食べにくい可能性があります。餌をふやかしてあげる、流動食に切り替えるなどの対策をおこなうことができます。
自分で身体を清潔に保つことが難しい猫には、毛並みを優しく拭いてあげる、失禁してしまった糞尿を速やかに片付ける、毛布や猫用ベッドが汚れたときはすぐに交換するなど、環境を清潔にするための行動によってQOLを維持します。
できる限り後悔を残さない
猫が死ぬまでの時間は思ったよりも短く感じてしまうものです。できる限りのことをしてあげましょう。動物病院での治療や、より良い生活環境での飼育をおこない、死期の近い猫では獣医師の指示のもと、標準的な食生活ではなく、できる限り好物や嗜好性の高い食べ物を与えてあげてください。
いつかその時はやってきます。どのような素晴らしい飼育をしていても、後悔することもあるでしょう。しかし、あなたのできる限りの愛情はかならず愛猫に伝わっています。後悔を残さないようにおこなってきたすべては、愛猫の生きた証として、そして飼い主のこれからの人生の支えとして、静かに力強く存在し続けます。
こちらの記事もご覧ください

どの動物種にも言えることですが、「死」というものは必ず訪れるのと同時に、死と向き合うときにいかに送り出すことができるかに最適な答えを見つけ出すことは非常に難しいものと思います。
言葉の通じない猫だからこそ、なんとかしてあげたい…そう思う飼い主の方はおおいのではないでしょうか?老衰であれ病気による衰弱であれ、できることならば苦しい状態から解放され少しでも安らかに過ごせる環境を整えてあげたいものです。愛猫に対して、愛情を惜しみなく提供し最期のお見送りができれば、その気持ちは必ず猫に伝わるものと確信しています。
プロフィール詳細を見る
まとめ
- 猫は死ぬ前、体調不調を表すサインをみせる。
- サインには行動の変化とバイタルサインの変化が含まれる。
- 行動の変化では普段の猫とは異なる様子がみられる。
- バイタルサインの変化では心拍、呼吸、体温などの変化がみられる。
- 死期の近い猫の体調の変化に気が付くこと、QOLを維持することは大事である。
- 体調の変化に気が付くことで、疾患の治療や老衰のケアをおこなえる。
- QOLの維持には猫の心や身体の不快さを取り除く意味がある。
- 猫が最期のときを迎える前に、できる限りのことをしてあげる。
よくあるご質問
-
Q
猫の死の直前の兆候は何ですか?
A心拍数や呼吸数の増減や体温の低下が起きます。
-
Q
家で飼っている猫でも死ぬ前にいなくなるのですか?
A猫が死ぬ前にいなくなるのは、防衛本能が原因ではないかと考えられているため、安全な家の中だけで飼育されている昨今は、死の直前に姿を消す猫が減ったとも言われています。
-
Q
猫の苦しそうな鳴き声も死の兆候ですか?
A猫は体調不良を隠そうとする生き物ですが、不安を感じると鳴くことがあります。このようなときは、よほど苦しいか痛みがあると考えられるため、死の兆候とも言えるでしょう。
※1:一般社団法人 ペットフード協会 2020年(令和2年)全国犬猫飼育実態調査 結果
https://petfood.or.jp/topics/img/201223.pdf(参照2021-6-18)
※2:A Conversation With Koko the Gorilla
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/08/koko-the-talking-gorilla-sign-language-francine-patterson/402307/(参照2021-6-18)
※3:猫における問題行動
https://www.jstage.jst.go.jp/article/dobutsurinshoigaku/26/3/26_101/_pdf/-char/ja(参照2021-6-18)
こちらの記事もご覧ください
※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数
この記事の執筆者

若林 薫氏
獣医師
ライター
若林 薫氏
獣医師
ライター
麻布大学を卒業し獣医師免許を取得、大手ペットショップで子犬・子猫の管理獣医師として勤める。その後、製薬企業での研究開発関連業務を経て、ライターとして活動する。幅広い専門知識を生かした記事作成を得意とする。
運営元情報
| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |
| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |
| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |
コラムの執筆と編集について
ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。
以下のページよりご確認いただけます。
【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/






 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ