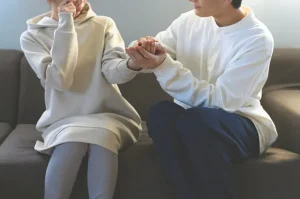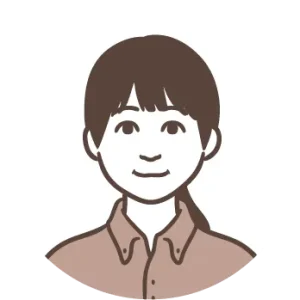2021.11.29
2025.09.23
犬が水をよく飲むときの原因は?考えられる病気の可能性を解説

犬が普段より水をよく飲むときや、散歩中やペットシートにした尿の量が多く感じるときは要注意です。多飲、多尿の原因には大きな体調不良を引き起こし死因になり得る疾患が含まれています。多飲、多尿のときみられる症状や、判断の目安、原因となる疾患について獣医師が解説します。
次のページで実際にお見積りをご確認いただけます
※弊社スタッフからご連絡させていただく場合がございます。
この記事の監修者
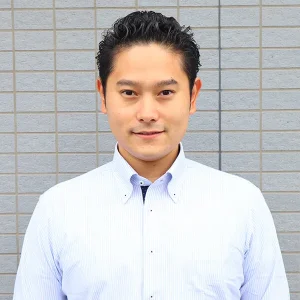
江本 宏平氏
株式会社 B-sky 代表取締役 / 獣医師
江本 宏平氏
株式会社 B-sky 代表取締役 / 獣医師
獣医師、犬猫の在宅緩和ケア専門、2012年日本大学卒
通院できない犬猫に獣医療を届けるため、往診専門動物病院わんにゃん保健室を設立。
短い時間の中で行う「業務的な診察」ではなく、十分な時間の中で家庭環境を踏まえた診療プランを提供できる「飼い主に寄り添う診察」を心がけています。
犬が水をよく飲む、おしっこをたくさん出す

犬の異常な飲水量と尿量の増加を多飲、多尿とよびます。多飲多尿はホルモンの乱れが引き起こす内分泌疾患や、内分泌を支配する脳機能の障害、尿を生成する重要な臓器である腎臓の障害などいくつもの命に関わる疾患の症状としてみられ、犬の健康を維持するために特に注意するべき点でもあります。(※1,2)
多飲と多尿の判断の方法
犬が多飲多尿だと判断できる基準はどれぐらい?
正常な犬において一日に必要な飲水量は体重1kgあたり20~90mlといわれています。これは5kg程度小型犬で100~450ml、10kg程度の中型犬で200~900ml、20kgの中大型犬で400~1800mの飲水量が必要になることを表しています。
一般的な計量カップや飲料水のペットボトルが500ml程度の容量であることを念頭にすると必要な飲水量のイメージがしやすいでしょう。
正常な犬における一日の尿量は体重1kgあたり20~45mlであり、必要な飲水量と同様か半分程度とされています。
一方、多飲と判断される犬の一日の飲水量は体重1kgあたり100ml以上だとされ、多尿と判断される一日の尿量は体重1kgあたり60ml以上だとされています。
多飲の判断をするとき、何を注意するべき?
多飲多尿の判断をする際に定量をおこなうことが重要です。
定量とはきちんと量を測り飲水量や尿量を把握することをいいます。たとえば、5kgの小型犬では一日の飲水量が500mlを超えたら多飲と判断できるわけですが、毎朝計量カップ1.5杯分の水、つまり750mlの水を空の水入れにいれ、次の日に残った水を計量カップで量を測定し残量が250ml以下だった場合、多飲と判断することができます。
定量をおこなうさいに気をつけなければいけないこととして、計量カップは犬用のものを使用する、水は予想される飲水量より十分にいれることが大切になります。犬が口をつけた水の中には人間にとって感染性がある細菌が含まれている可能性があります。人獣共通感染症を防ぐためにも犬専用の計量カップを用意しましょう。
多飲の犬は、身体が必要としているために水を多く飲みます。飲水量ぎりぎりの水だけ用意されている場合、水を飲み切ってしまうことがあります。身体にとって非常に大きな負担になるため、飲水量の測定をおこなう場合でも水は十二分にいれるようにしましょう。

多飲多尿を疑ったら、ご自宅で計量することもいいですが、できる限り早めに尿検査して尿比重を確認することをお勧めします。
事前に動物病院に相談しておけば、採尿キットをもらえると思いますので、そちらを準備しておきましょう。多尿は頻尿ではなく、トイレの回数はさほど多くなっていないが全体量が多くなっている状態であることを覚えておきましょう。頻尿であれば膀胱炎とかの話がでてきますが、多尿であれば怖い病気の話になることが多いです。違和感を感じたら、なるべく早めの通院を検討してください。
プロフィール詳細を見る
多尿の判断をするとき、何を注意するべき?
飲水量と比較すると尿量の定量は難しいといえます。尿はペットシートや野外の土に染み込んでしまうため、正確な量を測ることができません。普段から正常な尿量を把握しておくことが重要です。
また、尿量が多く増える多尿と区別がしにくい症状として頻尿というものがあります。これは尿量が増えるというより、尿の回数が増える症状です。さかんに尿をするしぐさをするが尿量が少ない、尿を我慢できず漏らしてしまう場合、頻尿が疑われます。
どのような場合、動物病院を来院すればいい?
明確に多飲や多尿の症状がでていなくても、飼い主の立場から何かおかしいと感じた場合、迷わず検査を受けさせましょう。また、頻尿などの他の症状がみられた場合も同様です。
症状に対してなるべく早く対処することで、あらゆる疾患の早期発見や早期治療に繋がります。
また、多飲多尿やその他の尿の症状で動物病院を来院する際はできるだけ新鮮な尿をビニール袋で密閉して持っていくと検査がスムーズにおこなえます。
いっしょにみられることが多い症状
多飲や多尿を引き起こす疾患は、嘔吐や下痢、発熱、元気、食欲の低下、外陰部からの膿の排出などのさまざまな症状を同時に引き起こす可能性があります。
多飲や多尿の原因となる疾患

クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
犬で一般的な内分泌疾患であり、ステロイド剤と同様の効果がある副腎皮質ホルモンが過剰に分泌される疾患です。
副腎皮質ホルモンを分泌する副腎に原因がある場合と、副腎にホルモンを分泌するよう命令する脳の部分である下垂体に原因がある場合があります。
中高齢の犬でよくみられる疾患であり、ミニチュアプードル、ミニチュアダックスフント、ヨークシャーテリア、シーズー、マルチーズ、シュナウザー、キャバリア、ジャックラッセルテリア、ボクサーなどが好発犬種として知られています。
この中にはプードルやダックスフントのように日本で多く飼育されている犬種も含まれています。
多飲多尿以外の症状として、お腹が膨れる腹囲膨満、脱毛、筋肉の萎縮、全身性の高血圧症などがみられます。
慢性腎不全
慢性腎不全は3カ月以上症状が続く腎機能の低下を指す疾患です。犬の死因としてよくみられる疾患です。中高齢の犬や歯周病の犬などでは発症リスクが高いといわれています。
慢性腎不全は進行性で不可逆性の疾患ですが、早期発見、早期治療をおこなうことで病状の進行速度を抑え、QOLをより長く維持できると報告されています。
ヨークシャーテリア、ジャックラッセルテリア、ホワイトテリア、ブルテリア、ボクサー、イングリッシュコッカースパニエル、シャーペイなどが好発犬種として知られています。
多飲多尿以外の症状として、嘔吐や食欲低下がよくみられます。そのほか、アンモニア血症による口臭や、腎機能障害による貧血、尿失禁、体重減少などの症状がみられます。
子宮蓄膿症
子宮に細菌が感染し、膿が貯留される疾患です。子宮蓄膿症の犬の60%は血液中への細菌感染症である敗血症を続発させ、ショック症状により犬を死に至らしめる可能性があります。未避妊、未経産の中高齢の雌犬でみられる疾患です。
多飲、多尿以外の症状として、外陰部からの膿の排出、発熱、元気食欲の低下、嘔吐、下痢などがみられます。
尿崩症
腎臓で生成される尿は、尿細管とよばれる腎内の構造で水の再吸収を受けることで濃縮され、できる限り老廃物の濃度を高く、体外に排出する水分量を少なくするように調整されます。これらの働きを担うホルモンをバソプレシンとよび、脳の視床下部―下垂体で生成分泌されます。
脳でバソプレシンが生成されない状態を真性尿崩症、腎臓でバソプレシンを受け取ることができない状態を腎性尿崩症とよびます。
尿崩症では尿が濃縮されなくなるため、著しい多尿が引き起こされ、脱水による多飲がみられます。(※3,4,5,6)
多飲や多尿かもしれない犬にしてあげられること

動物病院を受診する
多飲や多尿の症状がみられる犬では、内分泌疾患や腎疾患などの大きな原因が疑われます。できるだけ早くに動物病院を受診し、検査を受けるようにしましょう。
動物病院には新鮮な尿を持参するとより詳細な検査を受けることができます。尿の採取は紙コップで直接採取する方法のほか、裏返したペットシートにさせた尿をとる方法などがあります。
また、できる限り手を尽くしたが尿がとれなかった場合でも、動物病院で尿を採取する方法があるため焦る必要はありません。
愛犬の健康に不安がある場合速やかに獣医師の診察を受けましょう。

若齢のわんちゃんですと、元々飲水量が多い子が多いため、多尿傾向になります。多飲多尿に気づくファーストステップは普段からの“普通”を知っておくことです。
日常の中で当たり前のように水を準備しているかと思いますが、いつもの減りの早さ、ペットシーツのいつもの濡れ幅、などを知っておくと、違和感にいち早く気づけるかもしれません。
プロフィール詳細を見る

 もしもにそなえる生前見積もり
もしもにそなえる生前見積もり
ペットちゃんのもしもの時、慌てて悔いの残るお別れとならないよう、事前準備が必要です。ペトリィでは生前のご相談も可能です。

自宅での葬儀

家族立ち合い

セレモニー

家族でお骨上げ

骨壺に納めご返骨

霊園への埋葬
※1:埼玉県獣医師会 水の飲み過ぎは病気のサインかもしれません。
https://www.saitama-vma.org/topics/%E6%B0%B4%E3%81%AE%E9%A3%B2%E3%81%BF%E9%81%8E%E3%81%8E%E3%81%AF%E7%97%85%E6%B0%97%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8B%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%81/
※2:VETS TECH 犬の多飲多尿に対する診断アプローチ
https://vets-tech.jp/wp-content/uploads/2019/09/PUPD_vets-tech.pdf
※3:Diagnosis of spontaneous canine hyperadrenocorticism: 2012 ACVIM consensus statement (small animal)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24112317/
※4:Cushing’s syndrome—an epidemiological study based on a canine population of 21,281 dogs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6500859/
※5:Chronic Kidney Disease in Dogs in UK Veterinary Practices: Prevalence, Risk Factors, and Survival
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.12090
※6:Pyometra in Small Animals
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195561618300263?via%3Dihub
こちらの記事もご覧ください
※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数
この記事の執筆者

若林 薫氏
獣医師
ライター
若林 薫氏
獣医師
ライター
麻布大学を卒業し獣医師免許を取得、大手ペットショップで子犬・子猫の管理獣医師として勤める。その後、製薬企業での研究開発関連業務を経て、ライターとして活動する。幅広い専門知識を生かした記事作成を得意とする。
運営元情報
| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |
| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |
| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |
コラムの執筆と編集について
ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。
以下のページよりご確認いただけます。
【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/






 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ