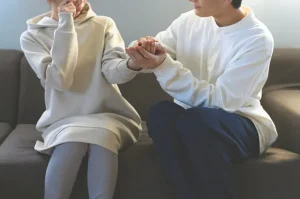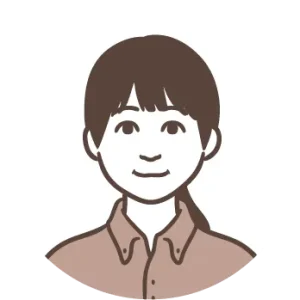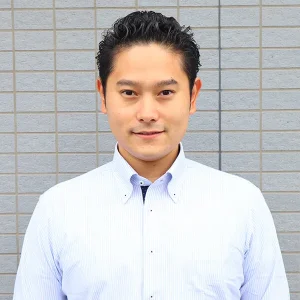2022.06.24
2025.10.17
フクロモモンガが突然死する原因とストレス死を防ぐための飼育の注意点

フクロモモンガはストレスに弱く神経質な動物です。そのため、死の兆候がわかりにくく、突然死が多いと言われます。フクロモモンガを長生きさせるにはどうすれば良いのでしょうか?死因や死の兆候、寿命、長生きの秘訣、飼育の注意点等について解説します。
次のページで実際にお見積りをご確認いただけます
※弊社スタッフからご連絡させていただく場合がございます。
フクロモモンガはストレスで死ぬ?突然死の原因とは

フクロモモンガは臆病でストレスに弱く、突然死が多いと言われる動物です。
まずは、フクロモモンガの死の原因から解説していきましょう。
死の原因は先天的な原因と、後天的な原因に分けることができます。
先天的な原因
先天的な原因は、フクロモモンガが遺伝子的に弱い場合と、病気を抱えている場合のふたつに分かれます。※1
死んでしまった場合は解剖をしなければ原因がわかりませんが、解剖をしてもわからないことも多いようです。※2
後天的な原因
死因の後天的な原因は多々ありますが、大きく4つに分けられます。
飲食物について
フクロモモンガは昆虫食傾向が強い雑食性の動物です。
野生のときは昆虫や幼虫、クモなどの節足動物、時には爬虫類や鳥のヒナ、卵や小型の哺乳類を食べています。
これらがいなくなる冬季(雨季)は、ユーカリやアカシアなどの樹液や樹脂、さまざまな植物からの浸出液、花蜜、花粉や花など植物性のものや分泌物、タマカイガラムシの甘い分泌物を食べ、糖質を摂取します。
ペットとしてのフクロモモンガにとって最良の食事は、タンパク質と果糖や樹脂などの炭水化物をそれぞれ50%程度与えることだと言われています。※3
好ましいフードは、フクロモモンガ専用フードや食虫目の動物用フードですが、中には穀物や乳製品が中心になっているフクロモモンガ専用フードがあるため、原材料を必ず確認するようにしてください。
特に、フクロモモンガは牛乳の乳糖を分解することができないため、与えてはいけない食べ物のひとつです。
できるだけ昆虫が入っているタイプのフードを使用してください。そうしたフードがない場合は、餌用昆虫をおやつとして与えましょう。
それらが手に入らないときは、高品質のキャットフードやモンキーフード、餌用昆虫、ピンクマウス、固ゆでした卵、赤身の肉などをタンパク質として与えましょう。
餌用昆虫は、乾燥したものも販売しているので、虫が苦手な方はこうしたものを利用すると良いでしょう。※3
フクロモモンガは、例え専用フードでも栄養が十分ではありません。タンパク質と炭水化物を50%ずつ与えなければならないからです。※1
これに加えて、入手できれば花蜜、花粉、アカシアやユーカリ、アラビアゴムの樹脂などを与えてください。
これらが入手できないときは、メープルシロップ、蜂蜜、新鮮な果汁やローリー用の餌などを炭水化物として与えましょう。 ただし、メープルシロップは気温によっては発酵することがあります。1日に1回は取り換え、夏季は1日に2回取り換えてください。
また、フクロモモンガは夜行性です。食事は夕方から夜にかけて与えてください。※3
お皿はひっくり返さないよう、ゲージに引っ掛けるタイプのものをゲージの高い部分に設置してください。
そうしたものがない場合は、重さのあるお皿を利用しましょう。
なぜなら、フクロモモンガが誤ってお皿をひっくり返し、からだがぬれてしまうと体毛により乾きにくく、体調を崩す原因になるからです。
給水ボトルを使用すると、使い方がわからず水を飲まないこともあります。体内の水が不足すると、フクロモモンガは12時間以内に死んでしまいます。できるだけお皿で与え、それでも水を飲まない場合はお皿を替えてみるか、モモンガ用ミルクやリンゴや完熟バナナのスムージーを与えてみてください。※1
特に、水道水は地域によっては塩素濃度などが高いこともあります。添加物はフクロモモンガの小さなからだに悪く、臭いによって飲まないことも考えられます。食事に関しても同じことが言えるため、添加物や農薬を過度に使っていない食べ物を与えてください。※1
そして、以下のものはフクロモモンガには絶対に与えないでください。
- シュウ酸塩が多い野菜例:ほうれん草、レタス、未熟なバナナ、ブロッコリー
- チョコレートなのどの人間用のお菓子
- 刺激の強い野菜・果物:玉ねぎ(ネギ類)、ニンニク、ニラなど
- 果物の皮、タネ、ジャガイモの芽等消化不良や中毒を起こす物
- 農薬のついた土がついたままの野菜・果物
- 牛乳
- スイセンやチューリップなどの花
- ジャガイモの芽
- カフェインの入ったもの(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)
フクロモモンガは群れで生活する社会性のある生き物なので、飼い主は毎日遊ぶ時間を作ってあげてください。
ただし、フクロモモンガは臆病なので、飼い始めは無理に抱き上げたり遊んだりせず、3日間はエサや水を与える以外は何もせずに、環境に慣れさせましょう。
飼い主の臭いが付いた布など安全なものを巣箱に入れるなどし、徐々に慣れさせてください。※4
特に生後半年~1年位の赤ちゃんのフクロモモンガを迎える場合は注意が必要です。
生後半年~1年位は腸や体温調整などの機能が未発達なので、環境の変化によるからだのストレスが原因で下痢を起こし、急死することがあります。
温度や臭い、飼い主、食べ物、ルーティン、ゲージなど、フクロモモンガは前にいた環境から新しい環境に来るときにこれだけの変化を受け入れなければならず、大いにストレスです。赤ちゃんなら尚更です。
赤ちゃんのフクロモモンガを飼育する際は、できるだけ以前居た環境と同じ温度管理、同じ構造のケージ、同じご飯、同じルーティン、同じのにおいの共有等をするほうが良いでしょう。
フクロモモンガの飼いはじめに体調を崩し死んでしまうことは少なくありません。生後2歳くらいまでは環境の変化に十分な配慮をしてください。※5
他にも、フクロモモンガを飼育する環境上で注意をすることはたくさんあります。
まずはゲージです。
フクロモモンガは活発に動き回るため、ゲージは大きめで縦長のものを用意し、中に止まり木やおがくずなどを入れた木製の巣箱を入れてください。
フクロモモンガは寒さに弱く、寒いと病気で死んでしまいますが、暑すぎても熱中症にかかるため、ゲージ内の温度は24~25℃の一定に保ちましょう。多少変化しても、23~25℃の間にし、急激な温度変化を避け、直射日光やエアコンの風が直接当たらないところにゲージを置いてください。※1
フクロモモンガは、排せつによるマーキングを行います。※4
不衛生な環境は病気の原因になるため、ゲージや止まり木などはまめに次亜塩素酸水を使って拭き掃除をしてください。
ゲージは最低でも月に1度は日光消毒や煮沸消毒をしましょう。
巣箱は3日に1度はおがくずを交換してください。※1
また、フクロモモンガは群れで生活します。2匹以上での多頭飼育がベストとされています。
1匹で生活させると飼い主に慣れていない場合や、1匹でいる時間が長いと孤独を感じ、ストレスで弱ってしまいます。
オスとオス、メスとメス、オスとメス、オスとメスとメス、どれも大丈夫ですが、メス1匹に複数のオスを入れることは大きなストレスとなるため避けましょう。野生では、オス1匹に対してメス数匹の群れを作っているからです。※1
夜行性のフクロモモンガを飼育する上で忘れがちなのが、日光(紫外線)です。
夜行性だからと言って日光を浴びないで生活できるわけではありません。日光を浴びなければビタミンD3不足に陥り、カルシウムが分解できずにクル病発症リスクが高まります。日中は窓やカーテンを開けてあげましょう。ただし、直射日光は避けてください。
クル病とは、日光やビタミン、カルシウムの不足により骨がもろくなる病気です。※6
人間が利用する照明は普通に使って問題ありません。光に関して避けるべきは以下の点だけです。
- 1日中真っ暗な室内にすること
- ペット用照明をゲージ内に取り付けること
- 日光を浴びさせないこと
※7
後天的な病気について
フクロモモンガの病気はさまざまですが、以下のものがわかりやすい例です。ただし、これらはどれも重症です。
- てんかん、発作、身震い
- くしゃみ、鼻水
- 下痢
- 目やに
- いぼなどのデキものや脱毛、皮膚の炎症
- カルシウムをはじめとした栄養不足・脱水
- 熱中症・低体温
※1
フクロモモンガはストレスに弱い生き物ですが、病気はストレスの原因になりやすいため、これらの病気や症状の全てが命に関わると思ってください。
中でも下痢や風邪は食欲不振によるショック状態や水分不足を招きやすくいずれも死につながります。食欲不振は数日、脱水は12時間以内に死んでしまうため、より早い対応が必要です。
事故について
フクロモモンガが飼い主に慣れてくると、一時的に放し飼いをして遊ばせることもあるでしょう。これは運動不足解消には良いのですが、事故には気を付けてください。
特に以下のことには注意をし、飼い主が見ているところだけで遊ばせましょう。
- 電気コードをかじられる
- 隙間に入って出られなくなる
- 食べてはいけないものを誤飲する
- 水を浴びてしまう(マーキングをするからと言って風呂場で遊ばせる際は特に注意)
- 壁などにぶつかって骨折や怪我をする
- フクロモモンガのパートナーとうまくいかず、咬まれる
- 他のペットから攻撃を受ける(木の上で生活しているため、特に地上にいる敵に疎い)
- 爪が引っかかって怪我をする
※1
フクロモモンガはほとんどの場合、爪切りの必要はありません。
しかし、遊び方によってはカーテンやタオルなどの布類に爪が引っかかり、指に糸状繊維がからみつく事故が起きることがあります。最悪の場合、指を切断することもあります。
爪が異常に伸びた場合や、こうした事故を防止したい場合は、動物病院で爪を切ってもらいましょう。フクロモモンガの爪には血管や神経が通っているため、いきなり飼い主が切ることは避けてください。※3
フクロモモンガに死の兆候はあるの?

フクロモモンガをはじめとした小動物は、外敵から身を守るために不調を表に出しません。
そのため、飼い主が気づいた頃には手遅れになっていることが多いため、フクロモモンガは突然死が多いと考えられます。
そのため、日頃から体調をよく観察することが大切です。
特に突然死の前は、以下のような兆候を示すこともあります。
- エサを食べない
- 水を飲まない
- 動かない・動いても弱々しい
- 聞いたことのない鳴き方をする
こうした兆候があったら、直ちに獣医師に相談してください。
老衰の場合は、このような兆候が少しずつ表れます。※1
フクロモモンガの供養について

残念ながらフクロモモンガが死んでしまったら、しっかりと供養をしてあげましょう。
供養は飼い主のペットロスを軽減する効果が期待できます。供養の時間を作り、手厚く弔ってあげてください。
フクロモモンガの供養方法は、土葬か火葬です。
土葬の場合は自宅の庭などで行ってください。公共の場所や他人の土地に土葬はできません。
火葬の場合はペットの火葬業者に依頼してください。
火葬は自宅に来てくれる訪問火葬と、霊園などの火葬施設で行う「霊園火葬」があります。
火葬だけのプランと、葬儀付きプラン、返骨のあるプランなどさまざまなものがありますので、自分に合ったものを選んでください。
フクロモモンガの寿命と長生きの秘訣とは
フクロモモンガの寿命は5~8年ですが、10年以上生きる場合もあります。※1
フクロモモンガを長生きさせるには、毎日の体調観察を欠かさないようにしてください。
例えば、以下のようなものをチェックすると良いでしょう。
- ご飯や水の減り
- フンの量や状態
- 怪我の有無
- 目や鼻の状態(色や乾燥具合)
- 皮膚の状態
- おなかが膨れていないか
※2
フクロモモンガの飼い方に注意点がある?
フクロモモンガは神経質でストレスに弱く、飼育環境を十分に注意してあげないと早死にします。特に体や年齢の小さいフクロモモンガには注意が必要です。
ここまで解説してきた飼育環境やコミュニケーション、飲食物、病気、事故などに注意をすると共に、かかりつけ医を持つことも大切です。
フクロモモンガを診てくれる獣医師はまだ少ないため、近くにそうした獣医師がいるかどうかを飼う前に確認してください。
まとめ
- フクロモモンガは臆病でストレスに弱い
- フクロモモンガの死の原因は、先天的な原因の他に、飲食物・飼育環境やストレス・病気・事故があげられる
- 突然死の兆候は、エサを食べない・水を飲まない・動かない・動いても弱々しい・聞いたことのない鳴き方をする
- フクロモモンガの供養方法は、土葬か火葬
- フクロモモンガの寿命は5~8年で、10年以上生きる場合もある
- フクロモモンガを長生きさせるには、毎日の体調観察を欠かさないようにするとともに、死の原因を減らすこと
※1:突然死が多い?モモンガが死ぬ前に見せる症状をご紹介
https://www.petkasou-happiness.com/column/post_column0102/
※2:人気急上昇のフクロモモンガ 飼い方の注意点と寿命について解説
https://psnews.jp/small/p/51065/
※3:フクロモモンガについて
https://miwaah.com/sugarglider.html
※4:モモンガの正しい飼い方って?保険で備えるペットの病気
https://www.nissen-life.co.jp/pet/contents/keep/279/
※5:フクロモモンガはストレスで死ぬ?ネットで検索されるストレス死についてのびも15が解説!!
https://nobimo15.com/blog/detail/20211216210041/
※6:フクロモモンガの寿命は5~8年!長生きさせる上手な飼育方法を解説
https://www.seikatsu110.jp/library/pet/pt_funeral/95970/
※7:フクロモモンガの死の原因となるストレスとは?解消につながる適切な環境を解説
https://animaroll.jp/small-animal/small-animal-knowledge/1132962?page=2/
※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数
この記事の執筆者

竹田 恵氏
ペットシッター士
ライター
竹田 恵氏
ペットシッター士
ライター
2017年よりライターとして活動中。子供の頃から動物好きで、猫、ハムスター、うさぎの飼育経験あり。現在はシーズー犬と一緒に暮らしている。犬は他の動物と比べて人間と密な生活になるため、ペット関係の資格を取得した。
運営元情報
| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |
| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |
| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |
コラムの執筆と編集について
ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。
以下のページよりご確認いただけます。
【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/






 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ